2022/12/28
1年の終わりに
こんばんは。横浜市港南区のカウンセリングルーム”キミィ・メンタル・サプリ”の萩原です。
2022年も残りあと3日、皆さんはいかがお過ごしですか。
別に大した感慨もなく年末まで働いて、残り数日もいつもどおりという方もいらっしゃると思いますが、大体の方は「あ~、今年の1年も早かった」などと言いながら、この1年を振り返ったり、大掃除をしたり、お正月準備をなさっているのではないでしょうか。
日本人は季節ごとの感覚や行事を大事にする民族だと思いますが、昨今はそうしたことに無頓着な若い方も多いように思います。
日々の生活に追われ、働くことや子育てに必死といった世代が、暮れも正月もなく食べるものも着るものもいつも通りというのも分からなくはないのですが、年長者としては少し寂しく感じています。
「忙しい」という漢字は「心を亡くす」と書きます。
節目の時には一度きちんと立ち止まって、今、来た道を振り返ったり、これからに思いを馳せたりして、整理整頓することがとても大切です。
今の生活はいつのまにか自分の思いや考えとは違っていたり、人に流されたりしていませんか。毎日を丁寧に誠実に生きてきましたか。
「そんなこと考える時間がないぐらい忙しかった」とか「そんな余裕のない生活だった」といって、日々を過ごしてしまうと、ある日、心が折れたり、「自分は何をやっているんだろう」などと人生の迷子になってしまいかねませんよ。
1年は365日、同じようでいて毎日違う1日1日の積み重ねで1年が過ぎていきます。
その大きな節目は12月31日と元旦といえるのではないでしょうか。
その時に初日の出を見に行ったり、初詣をしたりのように特別なことをしなくても構いません。
でも何も考えずに何も振り返らずに、次の年に突入してしまうのはいかがなものでしょう。
頑張った自分、努力した自分、変化した自分など、過ぎゆく1年を総括して、自分をねぎらったり、褒めたり、励ましたり、嘆いたりして、きちんと区切りをつけることをオススメします。
「いったん止まる」ことには意味があります。
そこで見えたこと、気づいたことにしたがって、次の年の舵をきるのです。
1年の終わりはその年の自分の保守点検の時だと思って、丁寧に過ごしていただけたらなと思います。
新しい年に誰かに相談にのってもらいたいという時は、いつでもお声をかけてください。
お待ちしています。
どうぞ佳いお年をお迎えください。

![1年の終わりに]()
2022/12/22
我慢は美徳ではない
こんにちは。横浜市港南区のカウンセリングルーム”キミィ・メンタル・サプリ”の萩原です。
今朝は冷たい雨が降っていましたが、いかがお過ごしですか。
さて、本日は「我慢は美徳ではない」というタイトルでお話いたします。
日本人の特性として「我慢することはいいことだ」つまり「我慢は美徳」とされてきたと思いますが本当にそうでしょうか。
一昔前の昭和世代は、そのまた一世代前の大正生まれや明治生まれの親に育てられたので、そうした「我慢は美徳」自分の思いや考えがたとえ違っていても、上からの言いつけや親からの言葉には従って「我慢して~する」「~年我慢すればやがて陽が差すとか好転する」といった考えが良しとされてきました。
しかし、自分の思いや考えを押し殺して生活することが習慣になってしまうと自分の意見は本当は何なのか、自分の願望は本当はどうしたいのか、そのことに対して怒りの感情があったはずなのに、あれはどこにいったのかというように、自分で自分の感情がわからなくなるという状態に陥ってしまいます。
もちろん自己中心的に何でも意のままに自己主張したり、協調性を欠いたりするのはよくありませんが、大きな力に対して巻かれたり飲み込まれることを良しとしてしまうと、戦う力をなくして、結果、体調不良や心の不調を抱え込むことになってしまいます。
人はある程度、喜怒哀楽の感情を表に出すなどしてストレスを下げる努力をしないでいると、体の内側にストレスが充満して、やがて体がSOSを発信してしまうのです。
不眠や食欲不振、わけもなく泣けてくる、人と関わりたくないなどはそうしたSOSのサインです。
もし、あなたに今、そうした兆候が一つでもあるなら見逃してはいけません。
自分で自分に問いかけてみてください。「どうした?大丈夫?」と。
我慢強いあなたは「大丈夫、私は平気よ」と答えるかもしれません。しかし、それは嫌なことや辛いことがあっても我慢することで乗り越えてきたあなたの性格のせいかもしれませんよ。
誰かに話を聴いてもらったり、全部吐き出してしまうことで、少しスッキリすると思います。
「我慢は美徳」は遠い昔のお話です。
もし、よろしければ、カウンセラーがあなたのお話をじっくりお聴きします。
是非、ためらわずに一度ご連絡ください。お待ちしています。

![我慢は美徳ではない]()
2022/12/14
自分の長所を忘れないで
おはようございます。横浜市港南区のカウンセリングルーム”キミィ・メンタル・サプリ”の萩原です。
本日は「自分の長所を忘れないで」というお題です。
あなたはご自分の長所と短所を5つずつ挙げてと言われたら、すぐに言うことができますか。
ひとつやふたつだったら言えるけど5つはちょっとという人も、長所は言えるけど短所は…、または、短所は言えるけど長所は…などさまざまな方がいらっしゃると思います。
また、長所は長じると短所になるということもあります。
例えば、「真面目」VS「融通が利かない」「頑固」
「慎重」VS「優柔不断」
「実行力がある」VS「自己中心的」などなど
こうした人の長所と短所ですが、カウンセリングルームにいらっしゃるクライエントさんにはある特徴があると感じています。それはご自分が短所ばかりになっていて長所は何もない、自信のない状態に陥っているということです。
大体の方は悩み事を抱えている時は自己肯定感が下がっていて、何をやってもうまくいかない、なんで自分はこうなんだろうと、ご自分のできないことや悪い部分ばかりに目がいってしまいがちです。
カウンセリングでは自己肯定感を上げ、自信を取り戻せるよう認知行動療法を使ったセッションを行いますが、その中で、ご自分の考え方や感じ方、行動を少し変えてみるということをします。
それはつまり、ご自分のいいところ、長所を思い出し、長所からのアプローチに変えるということなのです。
自分は何をやってもうまくいかない、ぐずぐずしていてものごとを決められないし前に進められないと後ろ向きに捉えるのではなく、ご自分の優しさ、協調性、思いやりの心などを思い出し、やればできる、やってみようと自分を信じて行動を起こすといった具合です。
自分に自信がない時は考えが後ろ向きになるので、前に一歩踏み出す勇気が出なくなるかもしれません。
でも、思い切ってカウンセリングを受けてみようと検索するとか予約するなどもひとつの前進です。
何かを変えようと思うなら、ご自分の長所、ご自分のできることを忘れずに、小さな一歩から歩み出してみましょう。
「自分ならできる」そう信じる心が未来の扉を開けることでしょう。

![自分の長所を忘れないで]()
2022/12/07
子どもの頃の自分に会いに行く
こんばんは、横浜市港南区のカウンセリングルーム”キミィ・メンタル・サプリ”の萩原です。
本日は「子どもの頃の自分に会いに行く」というタイトルですので、「どういうこと?」と不思議に思われた方も多いのではないでしょうか。
当カウンセリングルームは「認知行動療法」を主軸にカウンセリングをおこなっていますが、時と場合によって「空椅子の技法」という心理療法を実施することがあります。
「空椅子の技法」とはその名の通り、椅子を二つ用意し、目の前の誰も座っていない椅子に向かって座っていただき、そこに子どもの頃の自分を投影し、コミュニケーションをとるというものです。
この技法はクライエントさんの生育歴において、辛い出来事や悲しい出来事があったと思われる方に対して行われます。うまく子ども時代の自分と対面できたら、おとなになった自分が子ども自分に声をかけ、慰めたり、手をとったり、ハグします。それは子どもの頃の自分を癒すことが目的で行うものです。
「空椅子の技法」でその場にいない過去の自分に遭うという体験は誰でもできるというものではありません。
まずカウンセラーとの信頼関係が構築できているかがとても重要です。
他にも「空椅子の技法」は自分の意見を言えなかった相手に自分の考えや思いを伝えたり、相対するふたつの立場の自分を戦わせたりする時などにも実施することがあります。
小さい頃の自分に戻って人生をやり直したいとか、あの頃の自分に会って言葉をかけ励ましたいと思う方はたくさんいらっしゃると思います。実際には時間を巻き戻すことはできませんが、心の奥の深いところに働きかけ、ピンポイントで子ども時代の自分と交信することは可能です。
だいぶスピリチュアルな話になって懐疑的な方もいらっしゃると思いますが、心理療法の中にはこうしたものもあるということを今回はご紹介させていただきました。
ご興味があれば、是非お気軽にご相談ください。
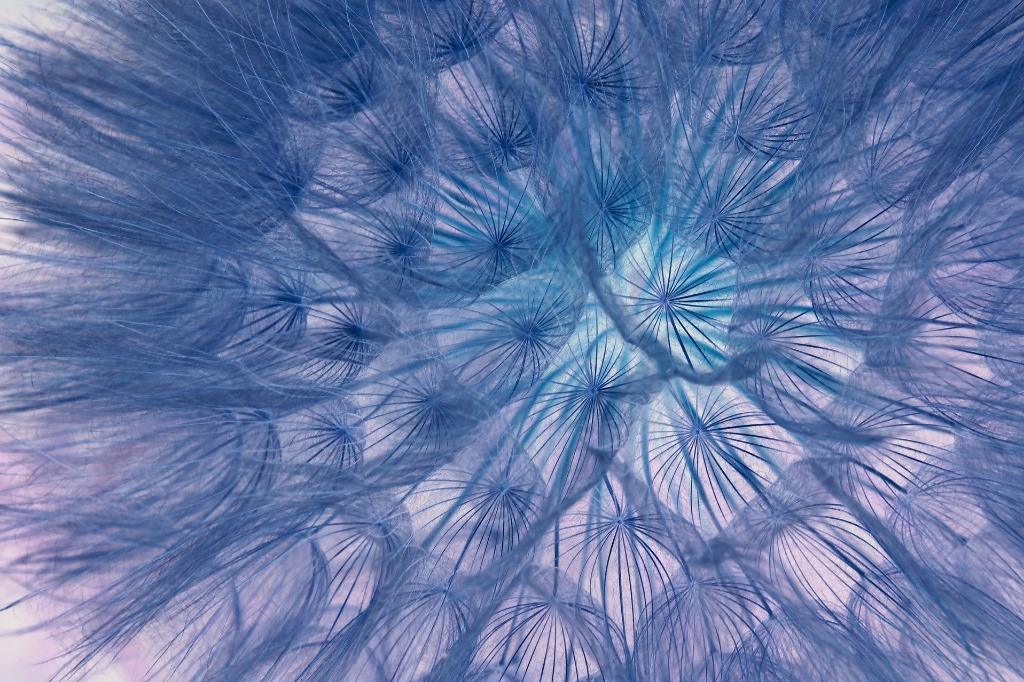
![子どもの頃の自分に会いに行く]()
2022/11/30
多重人格の自分を知る
こんばんは、横浜市港南区のカウンセリングルーム”キミィ・メンタル・サプリ”の萩原です。
本日は「ひとりの人間にはいろいろな人格が潜んでいる」というお話です。
人ひとりの中にはいろいろな人格があるということをお感じなったことがあるのではないでしょうか。
普段、温厚なのに、車に乗ると急に荒っぽくなって、スピードを出したり、前の車に異様に近づいたりするクセがあるなどというのもその一例です。
また、特定の人に対してだけ、意地悪になったり、高圧的になったりする人もいます。
もしくは「地雷を踏む」という言い方をよくしますが、何かをきっかけに怒りがこみ上げ爆発してしまうなどというのも多重人格的側面の表れです。
自分の嫌いな作業や苦手なことを前にすると、駄々っ子のような心理に陥ってしまう方もいます。
つまり、いつもの冷静さや穏やかな性格の下に邪悪で凶暴な一面が隠れていて、急に不安になったり、恐れたり理不尽を感じたり、または理由もないのになぜかその相手にだけ、まったくいつもとは違う性格が立ち現れることがあるのです。
それは誰もがもっている可能性があるもので、通常は理性でコントロールできているものが、何かのきっかけやシチュエーションによって、大抵はネガティブな側面がでてくるというものです。
臨床心理的にはこうした多重人格的側面の、自分でも手に負えないと思う性格や感情に名前を付けて何人かのキャラクターとして観察することを「モード・アプローチ」と呼びます。
「駄々っ子」や「泣き虫」「いばりん坊」「独裁者」「怒りの大魔王」など、もっとユーモアのあるネーミングやその人しか分からないエピソードからくる名前もいいですね。
とにかくそうやって自分の中にいる何人かのキャラクターを客観的に観察することで、自分という人物を理解することにモード・アプローチの目的はあります。
そうした困ったキャラクターは表に出そうになったらどうするか、どんな声をかければ収まるのかといったことを考えたり実践して、怒りや悲しみをコントロールする方法が手に入れられたらいいと思いませんか。
意外と自分で自分のことが一番わかっていないことも多いですし、自分が一番手強かったりします。
そんな時、カウンセリングという場でそれを解き明かし、自分が暴走したり爆発したりしないようコントロールすることを学びませんか。
ご興味のある方は、是非一度、お気軽にご来所いただければと思います。

![多重人格の自分を知る]()